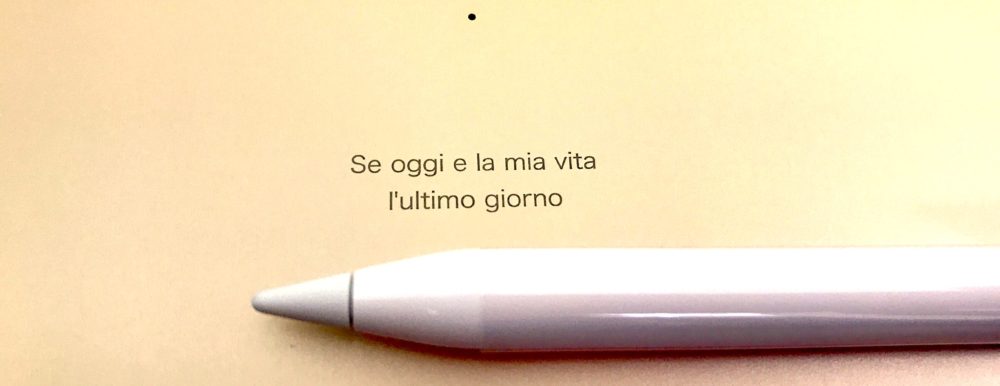NHK「私のこだわり人物伝」という番組の開高健さんの巻。開高健さんのことを気軽に「開高さん」とつい呼んでしまうのだが、実際お話したことはない。しかし、サン・アドに入社した時、サン・アドの社員名簿に開高さんの名前もあったし、山口瞳さんの住所もあったから、なんとなく勝手に「先輩」だと思って、「開高さん」と呼ばせていただいている。事実、サン・アドに入社が決まった時、まだ出社日より前にサン・アドのあったパレスビルを見に行ったことがあった。そのとき、大手町のオフィス街には似つかわしくない、麦わら帽子に短パンのおじさんとすれ違った。それがパレスビルから出てきた「開高さん」だった。
その開高さんの人物伝。これは録画しないわけにはいかないでしょう。その中で、印象的だったことをひとつ。
開高さんは悩んでいた。開高健、52才のとき。小説家として書くべき事を見失ったというのだ。
以下、番組より
——————————————
昭和58年芥川賞発表式で審査員だった開高さん。「今回は受賞作はなし」と発表した。開高健はこのころから文学への苛立ちをあらわにしていた。
文学作品は何をテーマにし、いかなる文体によるものであれ、何らかの意味での、反抗・復讐・批判・謀反・反乱、ひとえにこの情熱から書かれてきたが、今やそれらの敵を見事に失ってしまったのではなかろうか。今の、ソフト・オープン・リッチの時代に、その数少ないこと著しい。(開高健「衣食足りて文学を忘る」ふたたび!!より)
——————————————
書くべきテーマの喪失。
開高健さんが井伏鱒二さんの家を訪れる。そこでの会話。
開高「ちょっと教えていただきたいんですが、こりゃほんとに。
私は今、52才なんですが、
井伏さんが52才というと戦後すぐですよね。
人生はどういう風に見えたですか」
井伏「その頃は楽しかった」
開高「あ、あ、ころっと変っちゃった
何もかもひっくり返って」
井伏「うん」
開高「そうですね、井伏さんの世代の人は
あそこ(戦後)でいっぺん
活力を与えられましたね」
井伏「あそこで別な人間になった」
開高「はい、それは全くわかります。
初めからどんでん返しから始まっている。
私にはそれがない。
私、52才でどうしたらいいでしょうか。
しばしば夜更けに迷うんです」
井伏「書けばいいんじゃないすか?」
開高「枚数を」
開高「何でもいいから書くんですか?
いろはにほへとでもいい?」
井伏「ボクは、いろはにほへとを書こうと
思ったことありましたよ、書くことなくってね」
開高「それをちょっと教えていただきたくて」
井伏「書けばいいんだよ」
開高「書けばいい…」
井伏「うん」
開高「書く気が起こらないんです。
机に向かう気が起こらない」
井伏「そりゃぁ、あの、自嘲するからでしょ」
開高「はい」
井伏「良心があるから」
開高「良心とは大袈裟ですが。
良識をなくせばいいんですかね?
とにかく活力がない。野蛮がでてこない。
書くということは野蛮な…」
井伏「そうね」
開高「…図々しさが必要ですから…. 」
井伏「そうね」
開高「それが出てこなくて」
開高「洗練されてエレガントになっちゃって、
無気力になって、そのとき、
どうしたらいいでしょう….」
(番組ではここで終わっていた)
開高さんは悩んでいた。52才の開高健が先輩井伏鱒二に会いに行き、素直にアドバイスを求めている。しかし自分でどうすればいいかを薄々わかっているんじゃないかと思った。井伏さんに何かヒントを言って欲しかったんだろうが、実はその答えをわかっていて、それを確信したくて会いにいったんじゃないだろうか、と思った。井伏さんの答えにかぶせるようにしゃべっていた。ただのせっかちだとも言えるけど。
ボクも先日、とある先輩に会って悩みを聞いてもらうことがあった。(開高さんほど深い悩みではないにせよ)その時、ああしろこうしろという指示はなかっし、それを期待していたわけでもなかった。ただ、聞いてくれる人がいるという安心感が欲しかったのかもしれない。悩むということは、一生あるだろう。何歳になっても、悩むことはあるだろう。そのとき、話を聞いてくれる年上の先輩、同期の友だち、尊敬できる年下の後輩がいるということは、人生幸せなことだなと思った。