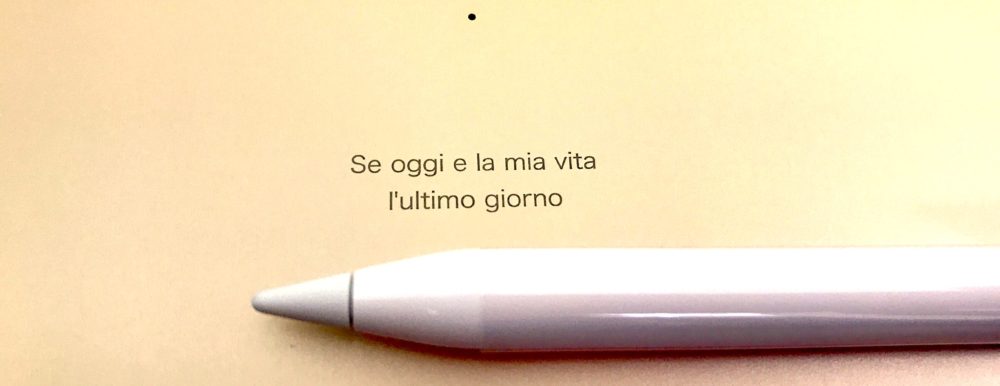CMを見て、その商品を買った。
CMを見て、その商品を買うのをやめた。
———————————-
先日クルマのタイヤを交換した。
点検したら、タイヤの溝に傷が入っているらしく
次の車検までには交換したほうがいい、というから。
現状に不満はないので、今と同じタイヤでいいかと思っていた時、
あるCMを思い出した。
ブリヂストンの『REGNO FEEL』
ブリヂストンという会社は、
もうずいぶん昔から独自の世界でレグノというタイヤブランドをCMで作ってきた。
たしかショーン・コネリーがCMに出ていた記憶があったので、
調べてみたらなんと、1981年新登場だった。
「そのCMで商品が売れるのか?」クライアントはまずそこを考える。
しかし、そこだけ考えていればいいのか?とも思う。
商品には「今欲しいもの」と「いつか買うかもしれないもの」とがある。
今欲しい人はCMの情報より、WEBなどから人の評判を収集する。
とくに高額になればなるほど広告より評判を信じる。
CMを見てすぐ家やクルマを買いに行く人はいない。
CMの重要な役割として
「いつか買うかもしれない人」の記憶にどう残れるか、があると思う。
(買ってみてダメだったら別のを買う、という価格の商品なら話は別だけど)
1990年、緒形拳さんが登場するKIRIN一番搾りデビューの頃のCM。
一緒に仕事をさせていただいたCMプランナー安西俊夫さんは
「15秒のCMに大事なのは、人の24時間のうち、
その15秒以外の時間に、いかに思い出してもらえるか、だよ」
と言っていた。
(安西さんの弟子でもあった岡康道さんも
『読後感』という言葉で同じことを言っていた)
REGNOのCMは、オンエアされていないボクの時間の中に確実に残っていた。
しかも、タイヤを買おうなんて思ってもいない時期に見たCMで。
商品の評判を調べてみると、静粛性がずば抜けているらしい。
(ちょっと値段は高いけど)
ユーザーの声に
「タイヤを交換したショップから道に出る、その段差で違いを感じた」
というコメントを見た。
さすがにそれは大袈裟じゃね?と疑ったけど・・・ホントだった・・・。
カーショップの駐車場を出てから数分走っただけで、
「なんかしっとりしてるゾ」と感じた。(気のせいかもしれないけど)
音楽を消して高速道路を走った時も「なんか静かじゃね?」と感じた。
(数値を調べたわけじゃないけど)

広告に騙されているのかもしれない。
でも、それでもいいと思う。
CMを見て、「あ、いいな」「好きだな」と思う。
「いつか買う時があったら、それも候補にしよう」と思う。
それはもう立派な広告の成果だ。
売上げの数字にすぐには現れない効果だ。
マーケデータというヤツには、この「将来買うかも」の人数はカウントできない。
広告は「いつか買うかもしれない人」のことを忘れてはいけない。
タイヤを換えるつもりもなかったある日に見た
ブリヂストン『REGNO FEEL』 のCM。
映像と音楽にブランドとしての一貫性を感じ、
その商品とその企業に好感を持っていた。
だからボクは、CMで、買った。
広告の競合プレゼンをして、
毎年表現が変わったり、方向性が変わったりする商品や企業がある。
商品を「こども」だとすると、
毎年違う「親」に育てられた「こども」がスクスク育つだろうか。
ボクにとって、REGNOという商品は、
ブリヂストンという家庭で、大切に育てられた「いい子」に見えた。
【余談】
タイヤのブランドは決めた。次は『どこで』換えるか。
カーショップはいろいろあるが、
家から一番近い、以前パンクの修理をお願いしたショップに決めた。
ひとつだけ「ここでは絶対買わない」と決めていたカーショップがあった。
それは、なぜか。
その会社のCMが酷いから。
例えREGNOが安くても、そこでは買わないつもりだった。
CMが酷い企業の売上に貢献してしまうと、
そのCMで良いんだ!と勘違いされると困るから。
ボクは、嫌いなCMの企業の商品は極力買わないようにしている。
広告の質の向上のために。